飛び恥とは、飛行機で移動することを批判する言葉。
元々はスウェーデンで作られたflygskam(フリーグスカム)=「飛ぶことの恥」という言葉で、flight shame(フライト シェイム)など英訳されて世界に広まった。
概要
飛行機に由来するCO2の排出量は2019年時点で人類の活動に伴う総排出量の2%を超え、鉄道や船舶などを超えるとされる。日本でも飛行機の排出量は1%を超え、やはり鉄道や内航海運よりも多い(ただし自家用車は航空機の9倍で運輸による排出の半分近くを占めるが) 。(出典:国土交通省)
国土交通省のサイトによれば、人が1km移動するのに排出する二酸化炭素の量は、自家用車が130g、飛行機が98g、バスが57g、鉄道が17gとなっている(2019年)。イギリスのデータでは、国内線の飛行機が255g、ガソリン自動車が192g、バスが105g、鉄道在来線が41g、ユーロスター(フランス・ベルギーとを結ぶ高速鉄道)が9gとなっている。
排出量にだいぶ差があるが、飛行機は座席数の差(日本は大型機が多い)や、鉄道は貨物列車の量(日本は貨物列車が少ない)などがある可能性がある。ちなみに日本の高速鉄道である東海道新幹線「のぞみ」は、JR東海によれば飛行機の1/12としており、ユーロスターに近くなる可能性がある。
いずれにせよ飛行機の排出量は多いことには変わりなく、飛行機移動を避けようとする意識・運動が「飛び恥」である。もちろんその中には極端に全ての移動から飛行機を除外する者から、必要性の低い飛行機移動を避けるというより現実的、あるいは妥協的な者まで様々である。
歴史
この言葉は2018年にスウェーデンで広まり、同国の環境活動家グレタ・トゥーンベリなどを通して北欧から西欧へ、また世界的に広まった。
グレタ氏はこの言葉ができる前の2015年から環境会議の開催地へ飛行機を使わない移動をしていると標榜しており、2019年にはアメリカの環境会議へ行くためヨットで大西洋を渡っている。
ちなみにその会議のあと、南米チリで開催されるCOP25に参加予定だったが、チリで反政府デモが激しくなり開催地が急遽スペインに変更されたため、ヨットをヒッチハイクしてヨーロッパに戻っている。
一方で、アメリカへ行く際に使用したヨットは修理のためにヨーロッパからスタッフが飛行機で渡米してヨーロッパへ回航し、船長は飛行機でヨーロッパに帰ったとも報道されている。
グレタ氏の行動は極端な中でも極端なものではるが、スウェーデンの空港運営会社によれば2019年1-4月のスウェーデンの空港利用者は8%減少し、鉄道の利用者が増加したという。
2021年には、フランスで「列車で2時間半以内に到達できる区間では飛行機路線の運航を認めない」法律が議会で可決。フランスは高速鉄道が充実していることが背景にあるが、一方で「4時間の壁」からすれば2時間半の距離はもともと鉄道シェアが大きく、影響は限定的かもしれない。
また2021年ごろからヨーロッパでは廃止された夜行列車を復活させる動きが出ている。これらも飛び恥に乗ったものだが、運営は赤字であるといい、どこまで持続的かはまだ見通せない状況である。
航空業界の対応
航空業界でもこれに対し対応は進めており、国際民間航空機関(ICAO)は毎年2%ずつ二酸化炭素排出量を削減することを目標としている。
まず飛行機そのものの排出量を減らす取り組みとして、機体の軽量化やエンジンの高効率化などがある。これらは運航コストを減らすことになるため、排出量が話題になる前から行われていた。また、燃料にSAF(Sustainable Aviation Fuel)と呼ばれる、バイオマス燃料などを使用した実質的に排出量をゼロとする燃料の使用などが進められている。
また、将来的には電動飛行機や水素飛行機を実用化することを目指して研究も進められている。参考:AMP(Yahooニュース)


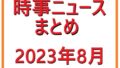
コメント